こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。
もうじきバレンタインですね。
今年もセイ夫婦、デパートの催事へ行ってきました。
セイ夫婦はもうね、その場で気に入った物を買いっこするスタイルです(買いっこて)。
去年の催事で食べておいしかったソフトクリーム、今年は更にかわいくなって出店するということで楽しみにしていたのですが、まさかの「昨日で完売」…。
でもチョコレートはほしい物が買えたので、よしとします。

さて、少し前の新聞やテレビで「デジタル遺言書が可能に!」と取り上げられていたの、みなさんご存知でしょうか。
なんでも、2026.1.20に要綱案がまとまったそうです。
これから国会に民法などの改正案を提出するので施行はまだ先になりそうですが、「おお、ついに…」と、仕事柄くいついてしまいました。
え、なに、すごいの? ていうか、そもそもどういうこと??
と思っている方、いらっしゃいますよね。
どういうことかというと、自分で作る遺言(自筆証書遺言)が、PCやスマートフォンで作成可能になるということなんです。
現行法で自筆証書遺言を作ろうと思ったら、それなりに手間がかかるんですよ…。
まず、全文・日付・氏名は手書き必須。PCを使っていいのは財産目録のみで、押印も忘れてはなりません。
ここまでも結構な手間ですよね。
そこから更に「自宅で保管するのは心配…」という場合は法務局で保管してもらえるんですが、これがまた…ルールーがね、細かいんですよ。
せっかく手書きしたのに、やり直し!(きぃっ!!)
ということがあるかもしれません。
まだ要綱案なので、PCやスマートフォンで作成する際の具体的なルールがどうなるのかは分かりませんが、それでも手書きをやり直すよりはきっとずっとラクですよね。
ちなみに、公証役場で専門家に作ってもらう遺言書(公正証書遺言)については、2025.10.1からデジタル化が始まっています(詳しくはこちら『公正証書の手続きがデジタル化されるってどういうこと?』)。
60歳〜79歳の遺言書作成率はおよそ3%だそうで、自分の予想よりずっと低くてびっくりしたのですが、このデジタル化によって遺言書を作ろうと思う人が増えたらいいなと思います。
実体験からの個人的な意見ですが、遺言書は、ないよりあった方がいいです。
父の時にちょっと大変だったんですよ(大変だった話はこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)。
いきなり遺言なんて言われても…。
という方は是非、エンディングノート(詳しくはこちら『スタッフセイ、エンディングノートを書いてみる!』)を書いてみてください。
「好きなこと」とか「思い出」とか書く欄もあるので、結構楽しいですよ。
そして、エンディングノートを書いていく中で疑問や不安が生じた場合や、
「やっぱり遺言を書きたいけど、3人の子どもたちにどう分けよう…」
などの具体的なお悩みが出てきた時は、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。
幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、終活全般に詳しいです。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。
ちょっとしょんぼりすることがあって、しょんぼりしたままお店でカフェラテを注文したら、こんなかわいい姿で出てきました。

よく行くお店なんですが、ラテアートがされて出てきたのは初めて。
なんでだろ。バリスタさんの気分?
偶然の出来事に、しょんぼりした気分も上向きになりました。
さて、先日、久しぶりに会った友人と近況報告で盛り上がっていた時のこと。
お正月休みのくだりで「うちの父親一人暮らしなんだけど、普段全然人と会話してないらしくて…」という話になりました。
あー…なんかそれ、前に同じく一人暮らしの義母も言っていた…。
会話するって、認知症予防の観点からも大事なことなんですよね。
そんな義母はこの年末、大掃除をしていたらトラブルになって、「でも管理人さんがお正月休みに入る前だったからなんとかなった」と言っていました。
えー…。
それ、数日遅かったらギリギリアウトだったんじゃない?
寒さに凍えながら(なんかこう、窓の上の方が突っかかって閉まらなくなったらしい)、防犯面もガラ空きのまま、お正月を迎えることになってたかもしれないんじゃない?
もうね、心配です。
ドキドキが止まらないです。
私たちもすぐに行ける距離に住んでないし、なんかないのかなー、と思って、ふと、少し前にやっていた情報番組を思い出しました。
訪問型見守りサービス…!!
定期的に家族の代わりに高齢者のお家を訪問して、近況を聞いたり、ちょっとしたお手伝いをしたり、簡単な認知機能のテストをしたりしてご本人の様子を確認し、家族に報告してくれるサービスです。
不審な業者から接触がなかったかも確認してくれたりするので、特殊詐欺の防止にもなりますね。
民間の事業者だけでなく、自治体がやっていたり、郵便局がやっていたり、ガス屋さんがやっていたりしますので、気になる方は是非調べてみてください。
他にも、宅配型見守りサービスというものがあります。
こちらは、宅配するついでに様子を見て、家族に報告してくれるサービスです。
運送や食材配送の事業者、お弁当屋さんなどが行っています。
あるお弁当屋さんのサービス内容を見ていて「おぉっ」となったのが、生活トラブル解決のプランがあること。
これいいんじゃない? 建具のトラブルもプランに入ってるし、緊急性の高いものは24時間対応してくれるし。
すぐにでも申し込みたい。
すぐにでも申し込みたいけど…。
そもそもお弁当の宅配…いるかな…(汗)
そう、あくまでサービスを受けるのは高齢者本人。
ご本人の意向が最も大切です。
私一人が盛り上がっても仕方がないので、ここは一旦保留にします。
ちなみにですが、義母宅には安否確認機器があります。これも、高齢者見守りサービスの一種です。
なので一応、家で一人で倒れて何日も誰も気付かなかった…!! みたいな最悪の状況にはならないようになっているんですね。
この安否確認機器もですね、色々なんです。機会があったら是非取り上げたいと思っています。
うちの親も離れた場所で一人暮らしだし、こういうの気になるけど…本人絶対嫌がるよなぁ…。
という方、きっといらっしゃいますよね。
「高齢の親が心配」「どういたらいい?」というお悩みがある場合、各自治体や地域包括支援センターに相談できます。
そして、その相談先の選択肢に入れていただきたいと思うのが、終活・相続・後見に強い行政書士事務所です。
幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、高齢者ご本人やそのご家族のサポート活動も行っており、終活全般に詳しいです。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。
みなさん、お正月はどのようにお過ごしだったでしょうか。
2026年も、どうか幸多き一年でありますように。

セイ一家はといえば、近場でちょこちょこお出かけしながら、基本的にのんびりとお休みを過ごしていました。
のんびりするには、のんびりのお供がいる…!
ということで、去年のお正月に製作して楽しかったので、今年も編みぐるみキットを買いましたよ。
今回は「あみぐるみストラップ」なるものをゲット。
小さなごまふあざらしを作りました。

やっぱり編み物いいですね。
没頭するんで肩はこりますが、とってもリフレッシュできます。
あとは、クリスマスに新しいジグソーパズルを買ってもらったので(ジグソーパズル好き)、それも作って我が子と楽しみました。
クリスマスといえば、今回のケーキは久しぶりのヒットで(毎年買ったことのないお店で購入している)とってもおいしかったのですが、もはや遠い昔のよう…(笑)
三が日には実家に行って親の元気な姿を見て安心したり、子どもがお友だちと楽しそうにスケートする姿をこっちも嬉しくなりながら見守ったり、季節限定のアイスクリームを食べて寒くなったり(ちゃんとあったかくしようね?)…。
誰も体調を崩さず、家族でゆっくりできたお正月でした。
2026年もはりきってお仕事に取り組みますので、みなさまどうぞよろしくお願いいたします。
公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録もぜひお願いします!

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。
今日はクリスマスイブですね。
みなさんはどのようにお過ごしでしょうか。
セイ一家は先日、毎年恒例のクリスマスマーケットへ行ってきました。
良いお天気で、クリスマス気分を満喫できましたよ。

さて、クリスマスが終わると一気にお正月モードですね。
ご実家に帰られたり、親戚で集まったりする方も多いと思います。
その時に、家族で将来のことを話し合ってみませんか?
なかなかねぇ、こういう話ってしづらいんですけど、かといって先延ばしにしていると、いざという時本当に大変です。うちの父の時もてんやわんやでした。
いやー、でもなぁ、うちの親、嫌がるんだよなぁ…。
うんうん、ありますよね。嫌がる親御さんは多いです。
うちの父なんて余命宣告されてましたけど、世間話の流れで「いざ亡くなったら」みたいな話をしたら「まだ死んでない!」と母が怒って、それっきり話が進みませんでした。
で、やっぱり大変でした。
どう切り出したらいいんだろう…。
という悩みを、以前所長の澤海に相談したところ、「うちのお墓ってどうなってるの?」という聞き方も良い、と教えてくれました。
うん。これはお正月に使いやすいかも。
初詣の流れでお寺や神社の話題になれば、そこからお墓の話に持っていけそうですよね。
あとは、「自分でエンディングノートを作って、新しいノートと一緒に親に話す」というワザも教えてもらいました。
これはですね、実証済みです。
親じゃないんですけど、たまたまエンディングノートを見つけて買って、それを自分で書いていたら、夫も「僕も書いておいた方がいいよねぇ」とその気になっていました(詳しくはこちら『スタッフセイ、エンディングノートを書いてみる!』)。
エンディングノートはハードルが高い…。
という方は、ひとまずパスワード帳を作ってみるといいかもしれません。
こちらも実証済みで(またもや夫)、やっぱり人がやっているのを見ると「自分も」という気になるんですよね。
お買い物サイトのパスワードとか、メールのパスワードとか、医療機関のパスワードとか、そういうのを書いているうちに、「銀行はどうだったかな?」とか、「あれ、全然使っていないキャッシュカードがある!」とか、気付いてもらえたらいいなと思います。
あとはですね、親戚で集まる機会があるのなら、是非、お葬式の話を取り上げていただきたいなと思います。
うちの父の時がそうだったのですが、死後に見つけた遺言でもなんでもないただのメモ帳に「直葬で」と走り書きがあったんです。
でも、父の兄弟たちは「お別れ会はしたい」という意見で、私たち姉妹は板挟みだったんですよね(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)。
なので、お葬式とかお墓とか、家族以外の人も関係してくる話は、お正月など親戚が集まる場で確認するのがおすすめです。
いやー、いやいや無理よ、将来の話とか。うちの親ガンコだから!
という場合は、専門家にアドバイスをもらうのも一つの方法です。
または、
「話は進んだけど、家をどうするかで悩んでいる。うちの場合は何が最善か知りたい」
「親はお墓を継いでほしいと言うけど、それはちょっと困る…」
「いやその前に実家の荷物多すぎ! 最優先事項は断捨離です!!」
という時も、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。
幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、終活全般に詳しいです。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。
あっという間に師走でびっくりしています。
なんなんですかね、この、歳を重ねるごとに年末が早くやってくるシステム(や、そんなことはないよ?)。
あれもこれもしなくては! と、バタバタしてしまいますが、そんな中で外せないのが、カフェなどに出てくるクリスマス商品。
先日も、通りすがりのドーナツ屋さんでかわいいスノーマンを発見したので、思わず買ってしまいました。

さて、以前ちょっと気になる記事を発見したので、今回のブログはそのことについて取り上げたいと思います。
その記事というのは、「座りっぱなしは認知症のリスクを増加させる可能性がある」というもの。
えー。
…まあ、でもなんか、そんな感じしますよね。座りっぱなしって、運動不足なイメージがありますし。
WHOも、日常的な長時間の座りっぱなしは、高血圧、脳卒中、心疾患、糖尿病などを引き起こすリスクがあるので気を付けましょう! と、言っていますし。
そもそも座りっぱなしってどれくらい? と思ったら、1日平均10時間だそうで、この日数が多いほど認知症のリスクが高まるそうです。
2025年5月にアメリカの研究チームが発表したところによると、座りっぱなしによって脳への刺激が減り、記憶を司る海馬の容積が早く減少する可能性が示されたそうです。
おお、なるほど。やっぱり体を動かすって大事。
「私は普段体を動かしているから大丈夫」
と思ったそこのあなた! 実は、要注意事項があるんです。
私もちょっと衝撃だったのですが、座りっぱなしにより起こる脳への影響と、運動していることは無関係なんです。
…え、無関係? それはつまり…??
つまり、長時間座っていた分運動しても、長時間座っていたことはチャラにならないんです。
えーーー。そこをなんとかーーー。
ほんとうにもう、えー、ですよねぇ。
なので、毎日しっかり運動している人でも、座っている時間を短くすることが大切になってきます。
理想は30分に1回、無理ならせめて1時間に1回、数分でいいので立って歩き回るのがオススメ。
そんな私は今、このブログを書くのにかれこれ1時間半くらい座りっぱなしですが…(あらあら)。
心がけることが大事かな、と思います。ストイックになっても疲れてしまいますので。
ほどほどに。できる範囲で。
この記事を読んでくださった方で、認知症に興味を持たれた方は、過去記事『知っておくと役立つ! アルツハイマー型以外の認知症』『お茶を飲みに出かけませんか? デイサービスより気軽に通える“認知症カフェ”のこと』や『家族が認知症になったらどうしよう? 後見制度の話』も是非ご参考になさってください。
幣所の所長である澤海は介護業界出身です。
介護や福祉についての専門知識がありますので、長い付き合いになる認知症について、この先どういった備えをしておいたらいいかなどのアドバイスもできます。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。
公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。
先日、憧れの食べ物に出会いました。
よく駅前なんかでやっている、期間限定の出店に偶然通りかかりまして。
そうしたらそこで売っていて。
一瞬、類似品かと思ったほど(なんで)。
でも、前でお会計をしているご婦人が、そばにいるご婦人に「これ本当においしいのよ〜」と話しているのを聞いて、間違いないと思いました。
私も早速購入。
値段に比してかなり小ぶり…。
とお会計をしながら思っていましたが、価値あり。
価値ありです…!!
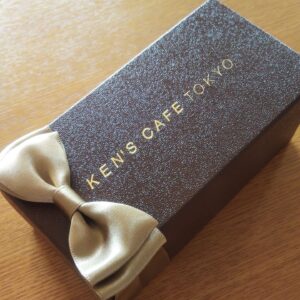
さて、今回のブログは、前回の『スタッフセイの脳ドック体験記 1』の続きになります。
一般的な健康診断の項目を一通り受け、脳ドックならではの検査も受け、認知症検査で非常に落ち込み…というのが前回までのお話。
いよいよ本丸、頭部MRIです。
まず、それまでつけていた自前のマスクを外し、病院で用意されたマスク(全く普通)につけ替えます。
次に、体に身につけている金属を外します。ヘアゴム、ヘアピン要注意です。
更に念押し、金属探知機でスキャン。
これでようやく、MRIのお部屋に入れます。
以前一度受けているので分かっていますが、頭部MRI、なかなかにうるさいです。
耳栓の上に頑丈なヘッドホンをつけて、ヘッドホンと自分を覆っている装置の壁との隙間にスポンジを詰め込まれてもうるさいんです。
誰かが台所で包丁を使っているような音がするなと思えば、次は日曜大工をしているようなトンカチの音、かと思えば工事現場のようなドリル音がしたり、突然毛色の違うシンセサイザーの様な音までしたりして、実に賑やかです。
ちょっとしんどいですが、20分ほどの辛抱。
画像に影響が出るということで、目や口の動きも制限されます。
私はもう、眠るつもりで(到底寝れないけど)ずっと目を閉じていました。
これが終わって、脳ドック終了です。
3時間かかる予定でしたが、2時間半かからなかったですね。
結果は、2~3週間後に郵送されます。
ちなみにお値段は、58,520円。
うーん、高い。
ですが、補助金が出たりする自治体もあるので、値段で敬遠せずに気になる方は是非調べてみてください。
さて、なぜ私が脳ドックを受けたかというと、10年以上前になりますが、母がくも膜下出血をやっているんですよね。
その時の主治医の先生に、「遺伝性のものもあるので、検査した方が良い」と言われまして。それで受けているわけです。
母のくも膜下出血は、本当にもう突然で。
「助からないかもしれないし、助かっても植物状態になるかもしれない」と手術前に言われていました。
ですが、ものすごい奇跡があって、後遺症はゼロです。先生にも「100人に1人だ」と言われました。
1%の奇跡…に頼るわけにはいかないので、こうして検査をしています。
備えることは大事です。…面倒なんですけどね。
でも、母が生死をさまよっている時、家族は大混乱でした。
あれがない、これはどうする、…保険証を見つけ出すだけでも一苦労でした。
みなさんも、ちょっと立ち止まって、「もしも」の時のことを考えてみませんか。
いやー、そんなこと言われてもねぇ…、検査は大変だし、何からすればいいのか…。
とお考えの方は、エンディングノート(詳しくはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)から始めていただくのがおすすめです!
私も書いてみたんですよ(『スタッフセイ、エンディングノートを書いてみる!』)。
自分の基本情報の他に、希望や要望が書けるようになっているのがエンディングノートの特徴ですが、書き始めると結構出てきます。希望や要望。
そうするうちに、「家を片付けたい」という衝動が湧いたり、「もしもの時、この家はどうするんだろう」という疑問が忽然と生まれたりするかもしれません。
「ここにあるお仏壇、子どもは引き継いでくれるのかしら?」
「自分が他界したら、家の名義はやっぱり妻にするべきか?」
「いやその前に家の片付け! …でも、量が多すぎる…良い業者を紹介してほしい」
などなど、疑問や不安なことがあれば、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。
幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、終活全般に詳しいです。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。
どんどん寒くなってきますが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。
私は、温かいお味噌汁でほっこりしています。
お味噌汁、セイ家では我が子が一番おいしく作ります。
子ども用の料理本に載っている通りに作っているそうなのですが、例えば私がそれを作っても、我が子のような味にはならないんです。不思議。
なんなんですかねぇ。なんか、我が子の手から特別なうまみ成分とか出てるんですかねぇ(笑)
ともかくおいしいので、時々お願いして作ってもらっています。

さて、この度セイ、脳ドックへ行ってきました! 人生2回目。
約6年振りということで、前回の検査とは内容も少し変わっていたりして、初めての検査もいくつかあったんですよね。
なので、今回はその脳ドックがどんなものだったのか、体験記として書いていきたいと思います。
私は今回、前回と同じ病院にネット予約をして受診しました。
ネットで予約すると、数日後に受診票やら問診票やら尿検査キットやらの一式が送られてきます。
検査開始は11:00で、朝食は7:00までに済ませてくださいとのことでした。
女性の下着はノンワイヤーとかだったらOKよ、という所もありますが、今回の施設はオールNG。素肌に検査着指定ですが、しっかりした厚手の素材なので全く問題ありませんでした。
さて、お着替えが済んだら早速検査開始です。
まずは血圧測定。
うわっ、たっかっ!
…まあ、分かっていたんですけどね。前回別の病院で測った時もそうだったので。
どうも私は「病院で測ると異常に数値が高くなる」という典型的な緊張タイプのようで。
自宅で毎朝測っている数値を伝えたら「その数値なら大丈夫ですね」とのことだったのですが…後日郵送される結果報告で引っかかっていたらいやだなぁと思っています(苦笑)
さて、脳ドックですが、ベースは普通の健康診断です。
採血とか心電図とか聴力とか…およそ健康診断と言われて想像のつくような項目は一通り行います。
そんな中での初めて1つ目。
頸動脈超音波。
けっ…けいどう…みゃく。
小学生の頃から2時間サスペンスをたしなんできた身としては、その言葉だけでもうドキドキです…。
それはさておき。
頸動脈は、脳に血液を送る大事な血管なので、異常はないか、硬くなっていないか調べるんですね。
診察台に仰向けに横たわり、首の喉を挟んで右と左でエコー検査をします。
エコー経験のある方は分かると思うのですが、あれ、くすぐったいんですよねぇ。
私はわけあって心臓のエコーも時々撮るんですが、もう、忍耐につぐ忍耐(笑)
でも、これで異常がないか分かるんですから、ありがたいことです。
さて、初めて2つ目は、MMSE(認知症検査)です。
簡単に言うと、記憶力の検査ですね。
今日は何日ですかとか、今いるのは何市ですかとか、まずはそんな基本的なことを質問されました。
あとは、目の前にペラっと紙を1枚置かれ、「これから言う通りにしてください」というのもあって、紙を折ったり床に置いたりしましたよ。
面白かったのは、「何でもいいので、紙に文章を書いてください」というもの。
え? 何でも??
と、最初戸惑いましたが、ちょうどその前日が我が子の誕生日だったので、そんなようなことを書きました。
文章を考えるのは好きなので、ちょっと楽しかったです(1行程度でOKですのでご安心を)。
で、超がつくほど落ち込んだのが、「100から7を引いていく」というもの。
血圧測定の一件でも分かるように、大分緊張しいの私。おまけに暗算それ自体が得意ではないときたもので、なんかもう、ぐっちゃぐちゃでした…。
きゅっ…きゅうじゅう…さん…?(そこからー!!)
頭、大混乱。
これは…引っかかったんでは…と、もうしょんぼりです。
ちなみに、帰宅してから家族の前で落ち着いて暗算してみせたところ、ちゃんとできました(うわーん)。
続いて、初めて3つ目は、ABI(血圧脈波検査)。
これは、足の動脈に詰まりがないか調べるというもの。
診察台に仰向けになって、両腕両足、4ヵ所いっぺんに血圧を測ります。
なぜ腕の血圧も測るかというと、腕の血圧と足の血圧を比較することで、詰まっているかどうかが分かるそうなんです。
4ヵ所いっぺんにということで、もう、ぎゅうぎゅうです。かつてないほどぎゅうぎゅう。
え、だったらもう、最初にやった普通の血圧測定しなくてよかったんじゃない??
と思ってしまいますが、検査内容がね、全然違うので、そういうわけにもいきません。
ちなみにこれ、2回計測するんですが、私は計測器の不具合があって3回やりました…。
さて、いよいよ本命の頭部MRIです。…が、大分長くなってしまいました。
続きは次回のブログにしたためますので、また読みにきていただけたらと思います!
そうみ事務所は公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです。

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。
先日、我が子の運動会へ行ってきました。
お天気にも恵まれ、我が子の成長に母は感動し、本人もホクホク顔で帰宅。
とっても良い運動会でした!

さて、先日、公正証書遺言の証人になってきたセイですが(詳しくはこちら『公正証書遺言の証人って何をするの??』)、その時に、「制度が変わった」というお話が公証人の先生からあったんですよね。
代表の澤海は当然承知していましたけれど、私は「具体的に説明して」と言われてもできないな…と思い、今回詳しく調べてみました。
変わったのは、公正証書の作成手続き。
令和7年10月1日から施行されています。
何が変わったのか? の前に、公正証書について少し。
公正証書とは、公証人が作成する公文書のことで、簡単に説明すると、ものすごく説得力のある(もしくは力を発揮する)文書ということになります。
仕事柄そうなりますが、私にとって身近なのは「公正証書遺言」(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)です。
他にも、売買や賃貸借の契約だったり、尊厳死宣言(自分の最期について意思表示すること)の際に作成したりと、公正証書には実に様々なものがあります。
そんな公正証書がどう変わったかというと、なんと、デジタル化されるということなんですね。
おお、公証役場にもデジタル化の波が…。
今までは、公正証書を作ろうと思ったら公証役場まで行かなければならなかったのですが、この改正によって、メールのやり取りやウェブ会議の利用で作成できるようになったんです(詳しくはこちら『公正証書の作成手続がデジタル化されます!』※日本公証人連合会のHPにとびます)。
「なかなか時間が取れない」とか、「遠方で行きにくい…」などのお困りが解消されるわけですね。
他にも、電子化に伴い押印が不要になりました。
押印不要はありがたい…!
あれねぇ…本当にもう、ここぞという時の押印ほど緊張するものはありません。そして大体失敗する(押印あるある)。
そして最も大きな変更は、「原則として電子データで公正証書を作成する」ということです。
完成した公正証書を電子データで受け取ることも可能ということなので、書類を管理する際の心配事(紛失や保管場所)も減りそうです。
とはいえ、ウェブ会議をするにもご自宅にその環境が整っていないといけませんし、メールのやりとりと言われても、そもそもそんなにインターネットを使わない方もいらっしゃいますよね。
ご心配なさらずとも、従来の対面での方式も変わらずありますので、ご安心ください。
逆に、「是非デジタル化を利用して公正証書を作りたい」という方がいらっしゃいましたらご注意ください。
10月1日より順次利用できるようになる、ということなので、お近くの公証役場がまだ対応できない場合があります。
ちなみにですが、公証役場では、公正証書を作成するまでの相談料が無料だということ、みなさんご存知でしょうか。
公正証書を作成する際の手数料はね、もちろんかかるんですが、そこに至るまでの相談は無料でできるんですよ。すごいですよね。
個人的に公証役場へ行って、公正証書を作ることは可能なんです。
とはいえ、例えば公正証書遺言を作成したい時に必要となってくる、遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本や預貯金の情報、不動産があればそれに関する証明書といった必要書類は全て自分で揃えなければなりません。
それ以前に、財産をどう分けるのがいいのか、悩まれる方もいらっしゃると思います。
「葬儀は長女に頼みたい。他の兄弟より財産を多目に遺そうと思うけど、それでいい?」
「お世話になった人にも遺したいけど、身内が納得するか心配…」
「もしかして、マンションの名義って、先に変更した方がいいのかしら?」
などなど、疑問やお悩みがある場合、弁護士や行政書士といった専門家に相談するのも一つの手段です。
え、公証役場へ行って相談すればいいのでは?
と、思われるかもしれませんが、公証役場で乗ってもらえる相談は、あくまで作成してもらう文書についてであって、その内容に関するアドバイスは残念ながらもらえないんです。
当事務所は、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。
公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。
久しぶりにレース編みをし出したら、楽しくて止まらなくなっております。
コースターとかお人形の手袋とか、小さなものをたくさん作って、つど達成感を味わうのが好きです。

さてセイ、この度なんと、公正証書遺言(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)の証人になってきました。
先生から打診された時には本当にビックリ。
しょ、しょ、しょ、証人っ?! 私がっ??? と。
しかしすぐに、これも良い機会。何事も経験! とポジティブに考え、「やります」とお返事しました。
ちなみに、今回私は「行政書士補助者」(詳しくはこちら『セイ、ついに補助者になる…!』)という立場で証人になってきました。
証人というのは、公正証書遺言が、遺言者の希望通りの内容になっているかどうか、ということをきちんと確認して、「間違いなく遺言者本人の意思が反映されている」と証明する役割を担っています。
公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要です。
今回は、澤海先生と私が証人となりました。
私の持ち物は、補助者証と認印。
公正証書遺言は、公証役場という所で専門家に作ってもらいます。
公証役場は、全国に300カ所あるそうです。
おお…公証役場…初めて行く…ドキドキ。
迷いそうだったので入念に調べて、時間にも余裕を持って出発したのですが、それはそれは、なんというかもう、近年稀にみる見事な迷いっぷりで。
自分でもびっくりしたのですが、電車から降りた瞬間から迷いました。
でもご安心を。
ものっっすごい時間に余裕があったので、ちゃんと約束の5分前には到着して受付を済ませましたよ。
公正証書遺言を作成するお客さま(遺言者)とご挨拶し、全員そろったところでお部屋に案内されました。
遺言者、証人2名、公証人の先生1名が着席。
すでに冊子の状態となっている公正証書遺言が遺言者と証人の前にそれぞれ置かれ、公証人の先生がその内容を読み上げます。
ふんふん、と公正証書遺言の文面を目で追うセイ。
時々立ち止まって、公証人の先生が遺言者に「内容に間違いはないか」とか「わからないところはないか」など確認していました。
なんせ公文書なんで、言い回しがね、やっぱり難しかったり、「ん?」と一旦考えないと理解できなかったりするんですよね。
たとえそれが自分の意思を反映している内容だとしても、ちょっとわかりにくかったりします。
内容がわからなければ、遠慮せずにその旨伝えましょう。大事なことですので。
公証人の先生も、きちんと丁寧に説明してくださいます。
そして無事、確認終了。
最後に、遺言者と証人が署名をします。
とここで、「実は、ちょうど今日から制度が変わりまして」と、公証人の先生。
おお、すごいタイミング。
なんでも、署名の際の押印が不要になったそう。
そんなわけで署名のみを済ませ、証人のお仕事は終了となりました。
公証人の先生からは、「この公正証書遺言の原本は、今日から100年、公証役場で保管されます」ということ、また、「データでも保存してよいか」というお話が遺言者にされました。
データで保存しておけば、万が一公証役場が火事になって原本が焼失してしまっても安心です。
諸々異存なければ、個人情報の取り扱いについて書かれた文書に、遺言者はサインをします。
それから、公証人の先生が一旦退席してしばし待つと…。
できあがりました!
公正証書遺言の謄本と正本です。それぞれ1通ずつ渡されます。
何が違うか簡単に説明すると、
謄本→原本の内容を丸々コピーしたもの
正本→上記に加え、かつ、原本と同じ効力を持ったもの
ということになり、通常は遺言者が謄本を、遺言執行者(遺言者の死後、その内容を実現する人)が正本を保管することになります。
その後、手数料の支払いをし、全て終了となりました。
お客さまと実際にお会いしてのお仕事ということで緊張しましたけれど、とても良い経験になりました…!
今後も新たな挑戦があればこうしてブログに書きたいと思いますので、みなさんもまた読みにきてくださると嬉しいです。
公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録もぜひお願いします!

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。
9月の下旬ごろからようやく秋の空気になってきましたね。
過ごしやすくて、お出かけもルンルンです。
そんなルンルン気分でお買い物をしていたところ、100円均一のお店でこんなものを見つけました!

さすが100均。何でもある。
要は、エンディングノート(詳しくはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)ですね。
中はこんな感じ。

自分や家族の情報、財産のこと、介護やお墓の希望、好きなことやエピソードを書くページもあったりして、驚きの充実さ。
そんなわけでセイ、この情報ノートをゲットして、記入してみることにしました。
なんとなく、最後のページをぺらり。
お、「もしもの時にこのノートを見てほしい人」って書いてある。
早速、夫とこどもの名前を記入(一文字も書いてないうちから)。
次になんとなく開いたのが「告知・延命処置について」(頭から埋めていく気ゼロ)。
ちょうど夫がそばでナンプレ(これも100均でお買い上げ)をしていたので、臓器提供や延命処置について一通り議論。
まとまらずに一旦保留にしたり、おおよそ二人の意見が一致したりしました。
隣が介護のページだったので、これについては迷わず記入。
「大事なものについて」は、主に棺に入れるかどうかについて話し合い、まとまらなかったのでこれも一旦保留。
保険なんかも、「契約内容一回見直そうか」なんて話にもなり、そばに家族がいるとはかどるなと思いました。
簡単なものですが、家系図作成欄もありましたよ!
家系図ってこう、繋がりが一目瞭然なので、第三者にとっては分かりやすくていいんですよね。夫にも書いてほしいなぁと思いました。
というよりも、なぜ夫の分も買わなかったのか…と後悔(笑)
記入したノートを夫に見せたところ、介護のページなんかは「僕もほぼ同じ」と言っていて、その後に、「僕も書いておいた方がいいよねぇ」としみじみ言っていました。
ちなみにですが、エンディングノートは各自治体で無料で配布していることがほとんどです。
区役所や地域包括支援センターなどで配布していますので、気になる方は是非調べてみてください。
「わざわざ行くのもなぁ…」という方には、無料ダウンロードもありますのでおすすめです。
私としては、とりあえず書いてみることが大事だと思うので、なんならもう、ひとまず家にある裏紙に書くのでもOKかと思っています。
そうすると、結構出てくるんですよ。自分の希望や要望が。
そうして書き出していくなかで、
「やっぱり遺言を書きたいけど、知識がないのでアドバイスがほしい」
「自分の代で墓じまいをしたいけど、どうしたらいいのやら…」
「物が多いから整理をしたいけど、よい業者さんを紹介してもらえないかしら?」
などなど、自分一人では難しいなと思った時は、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。
幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、終活全般に詳しいです。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。