こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
家で育てているレモンをそろそろ収穫しようかどうしようか悩み始めて2ヶ月が経ちました。(長っ!)
いやぁ、「もうちょっと大きくなるんじゃないか?」と期待して先延ばしにしていたんですが、その「もうちょっと」が全然こない…。
まあなんていうか、それ以前に真っ青なんですけどね。うちのレモン。
全っっく黄色くならない。
どうしようか、今でも悩んでいます。

さて、先日、NHKの「きょうの健康」という番組で、認知症予防のポイントについて放送していました。ご覧になった方もいらっしゃるかと思います。(「最新!認知症予防 14のポイント」※NHKのサイトへとびます)
番組では、2024年8月に発表されたとある研究について触れていました。
その研究内容は、「認知症のリスクは14コあるよ! この14のポイントを押さえていけば、認知症を最大45%予防できるよ!」というもの。
えぇっ、45%っ?!
すごいですよねぇ。私もビックリしました。
この14コあるというリスクは、生涯を3つの時期に区切った先に振り分けられます。
どんなリスクがあるのか、ざっくり説明しますね。
18歳までの時期にあるリスクは、ズバリ「教育機会の不足」
そう言われると、何か特別なことをしなくてはいけない気になりますが、学校教育をきちんと受けていれば大丈夫だそう。
ただ、学習するということは、脳を鍛えることになりますので、生涯に渡って学習していくことが大切になってきます。
私は何か学習しているのか…と考えて、そういえば、このブログを書くために毎回色々調べて勉強しているなとか、そう考えると事務所の仕事も日々学習だな…おお、すごいぞ。などとポジティブに捉えてみたりします。
新しい趣味を始めて、それを習得するのもとってもいいと思います。
新しい趣味…私も探しています。
さて次は、18~65歳までの時期。
この時期のリスクで同率トップは、「難聴」と「高LDLコレステロール」
難聴のリスクが高くてビックリしました。
聞こえづらいことで社会的孤立に繋がること、耳からの刺激が減って脳の働きが低下することなどが挙げられていましたよ。
高LDLコレステロールとは、いわゆる悪玉コレステロールのこと。
これが高くなると、アルツハイマー病の原因であるアミロイドβがより蓄積しやすくなるんだそう…。
最後に、65歳を超えた時期です。
この時期のリスクトップは「社会的孤立」
退職したり家族に先立たれたりして人との関わりが少なくなると、脳への刺激も減ってしまい、認知症のリスクへと繋がってしまいます。
この時期になっても何か熱中できる趣味があるといいなぁと思うセイです。
私の趣味、今のところインドアばっかりで…。
外に出て楽しめる趣味を見つけたいなと思っています。
さて、この記事を読んでくださった方で認知症に興味を持たれた方は、是非、将来のことも一緒に考えていただければと思います。
例えば、認知症が進行した場合に備えて後見人を選んでおいたり(後見人についてはこちら『家族が認知症になったらどうしよう?後見制度の話』)、エンディングノート(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)を作って大事なことを記録したり、自分の気持ちを書き出しておくのもおすすめです。
「後見制度について詳しく知りたい」
「自分の場合はどういった備えをしたらよいのか?」
「エンディングノートを書いてみたら、要望ややることがたくさんあった! 誰かにお願いしたいけど、どうすればいい??」
などなど、疑問や不安がありましたら、専門家にアドバイスを受けるのも一つの手段です。
幣所の所長である澤海は介護業界出身です。
介護や福祉についての専門知識がありますので、長い付き合いになる認知症について、この先どういった備えをしておいたらいいかなどのアドバイスもできます。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。
公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
セイ、少し前に誕生日を迎えました。
夫は毎年、律儀にカードとプレゼントとケーキを用意してくれます。
いくら私が「もう歳をとらないから必要ない。永遠のハタチ」と言っても、「うんうん、じゃあ、ハタチのお祝いしようね」と準備してくれます。
我が子からは「ハタチなわけないじゃん」と、いたって普通に言われます(うん、それが正しい反応)。
そう言いながらも、いつもかわいい絵を描いてプレゼントしてくれる我が子。
いくつになっても、祝ってくれる家族がいるのは嬉しいものです。
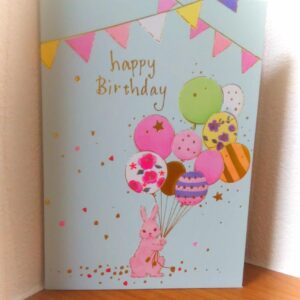
さて、先日、「父が亡くなった」という話を友人から聞きました。
その友人とは時々会ってお茶をする仲なのですが、私の父が他界した時に、死後事務がすごく大変だった話と「エンディングノート大事!」(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)という話をしていたんです。
そうしたら友人は、そんなセイ一家のドタバタを聞いて、お父さまにエンディングノートをすすめていたそうです。
お父さま、一部書いてくれていたそうで。
友人からは、「全部書いておいてほしかったけど、全くないよりは意味がある! エンディングノートをすすめてくれてありがとう」と言われ、私も役に立てたことを嬉しく思いました。
財産関連のことはお母さまが困らないように色々書いてあったらしく、死後にあちこち書類を探す必要がなかったそう。
うんうん、やっぱり事前の準備は大事ですね。
ただ、『遺影の写真に使ってほしい写真がある』という欄にチェックがついていたのに、肝心の写真がどれだか、探しても分からなかったそうで…。
容態が急変したということだったので、ご本人も後でゆっくり選ぶつもりだったのかもしれません。
ちなみに私の父の遺影は、いくら探してもいいものがなくてなくて…、結局、私の結婚式の時の写真になりました。
お葬式なのに、おめでたい写真…。
でも、参列した親族からは、「いい顔してる」「いい写真だ」と言われたので、よいこととします。
友人とは、「ある程度歳をとったら、遺影に使える写真というのも意識した方がよさそうだね」なんて話にもなりました。
お葬式のことなんかも、「なるべくお金をかけず、呼んでほしい人もいない」とあったそうで、友人も、「家族のためにも書き残しておいてもらえるとありがないなと思ったよ」と言っていました。
お葬式も、事前に何も決まっていないと本当にバタバタなんです。
私の父の時も、亡くなったその日に、葬儀屋さんのパンフレットを囲んで、どうするか家族会議をしました。
「早く決めなきゃ」の一心で、悲しむ余裕ゼロ。
そして、他にも死後にやることは山積みで…。(詳しくはこちら『100もあるって本当!? 死後事務の話』)
なので、事前に準備しておくというのはとても大切なことになってきます。
遺されるご家族のために、また、自身の希望を叶えるために、エンディングノートを書いてみませんか?
そして、書いているうちに、「ついでに身の回りの整理もしたいが…どうしよう?」とか、「終活って、私の場合はどこまでやっておけば安心かしら?」などの疑問が出てくるかもしれません。
そんな時は、専門家にアドバイスを受けるのも一つの手段です。
そうみ事務所では、生前整理や死後事務についてのアドバイス、ご相談も承っております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。
公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
毎日暑いですが、我が子は元気。
時間がある時は、朝早い時間に公園へ行って、一時間ほど遊んで帰ります。
真夏の遊具は灼熱になることで有名ですが、8時台だと鉄棒や滑り台もまだ全然熱くなく、ついでに人もいないので快適に遊び回る我が子。
付き添いの母は毎度ぐったりですが、子どもが楽しそうなのでよしとします。

ところでセイ、ついこの間とんだ目に遭いまして。
びっくりし、大慌てで対応し、解決して精神的にドッと疲れた果てに得た教訓を、ここに記しておこうと思います。
ある日のこと、クレジットカード会社からこんな感じのメールがきました。
「○○ストアで2万8千円の利用金額が発生してるけど、オッケー? 間違いなかったら、以下の認証コードを入力してね☆』
と。
いやいやいやいや、オッケーじゃないよ?!
○○ストア? 知りませんけど??
すかさず専門職の夫に連絡して、このメールが本物か調べてもらいました。
で、メール自体は本物で、と、いうことは、私のカード番号が漏れた…ということが判明。
すぐさまカード会社に連絡。
私はキャッシュカードと一体になっているものを利用していたので、コールセンターの人に、「止めちゃって大丈夫ですか? 一旦、現金を下ろしに行かれますか??」と、ものすごく念押しされたのですが、「いいです!いいです! もう、すぐ止めてください!!」と、こちらも猛プッシュ。
そして無事にカードを停止し、その日のうちにスマホからカード再発行手続きをし、ありがたいことに一週間かからずに新しいカードが手元に届きました。
もう本当に、ドッと疲れました…。
カード会社から確認メールがきたので(2段階認証バンザイ)、被害額としては再発行手数料の600円ほど。
しかし、これに費やした時間と、精神的苦痛は大きい…!!
しかも私、ネットからカードでお買い物なんて、するとしても年に2回くらいなんですよ。
まあ、回数なんて関係ないですが、一体どこから漏れたのかがナゾで。
新しいカードも届いたことだし、もう今持っているネットショッピングのアカウントはみんなきれいにしよう! と、スッパリさっぱり、バンバンアカウントを削除しました。
以前、パスワード帳を買って整理した時には、「今全然使ってないけど、このショップはまた利用するかも?」と、残しておいたアカウントが多かったんですよね。
で、そのうちの一つのサイトにアカウント削除目的で入ろうとした時、
『不正アクセスによるシステム侵害発生のお詫びとお知らせ』
というのが最初に出まして。
うわー! これかもーーーー!!
え、でも普通、通知こない? 見逃してた?? わからん!!
という状況です。
まあとにかく、ほったらかしはよくないよね、と思いました。ものすごく。
私はパスワード帳を作って満足してしまいましたが、時々チェックして、定期的に整理することが必要だなと痛感しました…。
また、パスワードを管理しておくことは、死後事務においてもとても重要です。
パスワードの整理をしながら、「口座もいくつかあるからついでに書いておきたい」と思った時は、エンディンノート(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)がおすすめですよ!
そうみ事務所では、生前整理や死後事務についてのアドバイス、ご相談も承っております。
エンディンノートを書き進めていくうちに、「こういう時はどうするの?」「死後事務や相続についてもっと知りたい」と思った方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。
公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
今年も行ってまいりました! 大本山總持寺での「みたままつり」!!
今年は混雑緩和のため、道の片側のみ屋台が出ていましたよ。
でもすごい人!
我が子は人生初のりんご飴を実食。
「買ってくる!」と言って、数分後に戻ってきた我が子が手にしているものを見て、母ビックリ。
りんご飴がすごいオシャレ。
思わず写真撮っちゃいました。

さて、先日のセイ夫婦、「そろそろ結婚指輪を洗浄しに行きたいよね〜」なんて話をしていたのですが、そこから、「自分が死んだら結婚指輪をどうしてほしいか?」という話に発展しました。
というのも、去年父の葬儀をした際に、「副葬品について考えておくことって大事だな」と思ったからなんです。
副葬品とは、故人と一緒に棺に入れる品物のことです。
父は急死して、本当にみんなバタバタとういか動転していて、そんな中、姉が副葬品を実家から持ってきてくれたのですが…。
ほとんどのものが、「これはちょっと棺に入れることはできません…」と葬儀屋さんに言われてしまいました。
や、本当に動転していて、とにかく「父に縁のあるもの」というその条件のみで選んできてくれたんですよね。
父はクラシック音楽好きで大量のCDを持っていたので、中でもお気に入りのCD数枚と、ずっと愛用していた眼鏡と、手紙と…という感じでした。
でも、葬儀屋さんに言われてそこで気づいたんです。
「燃やせないものはダメだよね」と…。
そこで今回改めて、棺に入れられるのはどんなものか? を調べてみました。
とにかくまずは、「燃やせるもの」です。
そう、それは当然ですよね。
でも、慌てていると忘れちゃうんですよ…。
しかし、例えばお洋服は燃やせますが、そこに革製品がついているとNGですし、食べ物も燃やせますが、瓶や缶に入っていたり、スイカなど水分を多く含むものはNGです。
他にも、燃やせるけど燃えるのに時間がかかるものや、大量に灰が出るものも棺に入れることができません。
これはOK? NG? と迷った時は、必ず葬儀屋さんに相談しましょう。
そして、そもそも入れられないものは、「燃やせないもの」です。
貴金属、ガラス、革やビニール製品、入れ歯、ピースメーカー、燃やすと有毒ガスが出るものなど。
そんなわけで父の眼鏡もNGでしたが、葬儀屋さんから「骨壺に入れましょう」と提案していただいた時には「え、骨壺に入れられるんだ?!」と、驚きました。
骨壺に全ての骨を納めたあと、父の眼鏡をその上に置き、蓋をしてもらいましたが、それで俄然「父らしさ」が出て、なんだかどう説明したらよいのかわかりませんが、とにかく「よかったな」と思ったのを覚えています。
親戚もみんな、「入れてもらってよかった」と言っていたので、よい選択だったと思います。
骨壺に入れられるものにも限度がありますので、こちらも必ず、事前に葬儀屋さんに相談することをおすすめします。
さて、冒頭の結婚指輪問題に戻りますが、結局、「仏壇に飾る」で落ち着きました。
そしてこの時、棺になにを入れたいか? や、骨壺になにか入れる? 入れない? という話までできて、お互いの希望を聞けたことがよかったなと思いました。
ここでさらに一歩踏み込んでおきたいのが、そうして話し合ったり考えたりしたことをエンディングノート(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)に書いておくことです。
これをしておくと、話し合いの場にいなかった親族にも自分の考えを伝えることができます。
エンディングノートには副葬品のことだけでなく、覚え書きや要望、様々なことを書いておけますので、とても便利です。
そして、書いているうちに、「生前に家財を整理したいけどどうしよう?」とか、「そもそも、葬儀ってどうやって選んだらいいんだろう?」などの疑問が出てくるかもしれません。
そんな時は、専門家にアドバイスを受けるのも一つの手段です。
そうみ事務所では、生前整理や死後事務についてのアドバイス、ご相談も承っております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。
公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
梅雨も明けないうちからなんて暑い…。
ということで、久しぶりにレアチーズケーキを作りました。
100gのクリームチーズで作る小ぶりサイズ。
少ない材料で作りやすいのでオススメですよ!

さて、この時期怖いのが「熱中症」ですよね。
先日、NHKの番組で熱中症についてやっていたので、勉強のために見ました。
なんとなんと、昨年(2023年)は、およそ9万人が熱中症で救急搬送されたそうで、その半数以上が65歳以上なんだとか。
見ていて、「はー! これは是非うちの親にも伝えよう!」と思ったのが、「湿度計と温度計を使うこと」
色々な理由でエアコンを使いたがらない高齢者の方は多いかと思いますが(私の親もそうです)、部屋に湿温度計を置いて、一定の数値(温度は28℃、湿度は70%)を超えたらエアコンをつける、と決めておくのがいいそうです。
そしてセイ、番組を見て思ったんです。
「救急搬送された時って、家族にどう連絡がいくんだろう?」と。
というのも、先日義母が道で転んで骨折したと聞きまして、肝を冷やしたところなんです。
本人がねん挫と思うくらい軽い骨折だったので大事に至らなかったのですが、頭を打って意識不明で運ばれていたら…? と思うともうドキドキです。
なにせ義母は一人暮らし。
もしその時に身元の分かるものを持っていなかったら、一体どうなってしまうのか…。
で、ちょっと調べてみました。
やはりまずは、お財布などを調べて、運転免許証や保険証を探すそうです。
あとは、医療記録から情報を探ったり、どうしても家族への連絡先が分からない時は警察に連絡して調べてもらうんだとか。
救急搬送については先生からも、
「私も講座ではいつも、お財布に緊急連絡先・既往歴・お薬の情報が分かるように入れておいてくださいね! とお伝えしています」
との意見をいただきました。
ああ、やっぱりそうなんですね。
そして、そう! 既往歴やお薬の情報、これ大事です!
私の母は10年以上前にくも膜下出血で倒れて緊急手術をしたのですが、本当にもう、既往歴から何から、分からないことだらけで大変でした。
「母の保険証が見つからない」から始まり、飲んでいる薬(毎朝何かを飲んでいるのは知っていた)も、お薬手帳の有無も分からない。
薬のアレルギーはあるのか、義歯(口にチューブを入れる関係で聞くんだとか)はあるのか、全身麻酔薬の経験はあるのか…。
看護師さんに聞かれる度に、「はい…」とか「多分…」とか、あいまいな回答しかできませんでした。
そんな教訓を生かし、セイ夫婦は「基本情報」というものを紙に書いて共有しています。
名前や生年月日といった基本情報に、先ほど記述した内容はもちろん、保険証やお薬手帳の保管場所、持っている疾患や家族の病歴、そして是非はっきりさせておきたいのが「医大での研究に使ってよいか」ということ。
母の時にも聞かれましたが、「いやぁ、これはさすがに本人に聞かないとね…」ということで、「いいえ」にしました。
とにかくそういったものを全部書き出し、机の引き出しにしまってあります。
我が子にも、「もしもの時はこれを必ず病院の人に渡すように」と言ってあります。
話は戻りますが、そんなことがあって一人暮らしの義母がますます心配なセイ。
夫に聞きました。
「おかあさん、ちゃんと緊急連絡先を書いた紙とか持ち歩いてるのかな??」
「えー、どうかなぁ、持ってないんじゃない?」
のんきー!!!
ということで、思わず持ち歩きたくなるようなかわいい緊急連絡先カードを我が子と作って、義母にプレゼントする計画が進んでいます。
みなさんも、いつ起こるか分からない緊急事態に備えてご家族と話し合ってみてはいかがでしょうか。
「改まって話すのは気恥ずかしい…」とか、「ちょっと気が進まない…」という場合は、エンディングノート(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)を書くのもおすすめです!
そうみ事務所では、「もしも」に備えたアドバイスやご相談も承っております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。
公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは!
横浜・鶴見・川崎の介護系行政書士のそうみです。
ようやく12月らしい空気になってきましたね。
急に冷え込んだので、体調を崩された方も多いのではないでしょうか?
何かいつもより変?と違和感を覚えたら、はやめに心身を休めてあげてくださいね。

さて、先日久しぶりに対面でのセミナーを開催しました。
テーマは、親御さんの老後が心配になってきた世代の皆さま向けの【エンディングノートのはじめかた】。
生協会員さん限定のセミナーでしたが、少人数でアットホームな雰囲気の中でお話できたかなと思います。
人数の多いセミナーだと講師と生徒として一方的な講義になりがちですが、
少人数だとおひとりおひとりのお顔や反応を見ながらお話できますし、それによって話す内容を微妙に変えられたり。
参加者の方のリアルなご相談をみんなで共有できたりと、個人的には少人数でのお話の方が好きです。
来てよかったです!と感想をいただけるだけでもとっても嬉しいですが、
なかなか話しづらいご家族間の介護や終活のお話を、
その日初めて会った皆さんの前で『聞いてもらってもいいですか?』みたいな形でお話してくださったりするときに
今日やってよかったなあとしみじみと感じます。
まずは誰かと話すだけでも、お話を聞いてもらえるだけでも、すごく気持ちが軽くなったりするのですよね。
少人数での勉強会の開催や、オンラインでの開催も可能です。
お友達同士や、町内会などのみんなで一度話聞いてみたい!
職場のみんな向けにセミナーしてもらいたい!
そんなご依頼も可能ですので、お気軽にお問合せくださいね♪
公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
すっかり空気が秋になりましたね。
未だに投薬中の我が子ですが、それでも随分元気になって、学校へも行けるようになりました。
「食欲の秋」ということで、久しぶりに夫&我が子が大好きなレアチーズケーキを作って、ひゃっほいしてもらいました。

さて、私の父は余命宣告を受けて、亡くなるまではずっと在宅看護でした。
亡くなったのは本っっ当に急で(身内は全員度肝を抜かれました)、バタバタのわちゃわちゃ。
救急搬送に付き添ったのは姉でした。
そこで突きつけられたのが、「延命装置を外すかどうか」の決断。
意見を聞きたくても、誰とも連絡がつかず(早朝4時前でした)。
おまけに、車を飛ばして向かっているはずのもう一人の姉はまだ病院に着かず。
それでも、「延命装置を付けていてもほとんど意味がないので早く決めてください」と、看護師さんがまぁぁ急かす急かす。
で、
決断しました。
一人で。
「外してください」、と。
姉は未だに罪悪感を持っています。
延命について、父は何も言っていませんでした。
後から見つかったメモ帳にも、そんな記述は一切なく。
少し、考えておいてほしかったなぁと思います。
ちなみに、母の希望ははっきりしています。
ドラマなんかでそういった医療シーンがあると必ず、
「お母さんはこういうのしなくていいから」
と、私が小学生の頃から言っていました。
本当に必ず言っていました。
父に関しても、チラッとでも口頭で意思表示するなり、話すのが嫌なら殴り書きでもチラシの裏紙でも、なんでもいいから形にしておいてほしかったなと思います。
そうすれば、父の希望を叶えることができたし、姉も罪悪感を持たずに済んだはず。
でも、改まって意見を聞いたり話したりするのって、気が進まなくてうまくいかないことがありますよね。
母のように、日常生活の中で話の切り口を見つけて意思表示や確認ができるとスムーズかもしれません。
または、エンディングノートを書いて、自分が寝たきりになるなど万が一があったら見てくれるよう、親族に頼んでおくのもおすすめの手段です。(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)
とは言え…
「口ではああ言っているど、本当のところはどうなんだろう」
「直接伝わっていない兄弟や親族に何か言われたらどうしよう」
という心配はあります。
私の母も、延命についてはおそらく私にしか話していません。
いくら小さい頃から刷り込まれているとはいえ、いざという時にはためらう自信が大いにあります。
「本人の希望を尊重し、かつ身内に後悔させない、罪悪感を持たせない」という目的のためには、口頭やエンディングノートだけでは足りないと、そうみ事務所では考えております。
え、じゃあどうすればいいの??
ご心配なく!
方法はちゃんとあります。
そのことについては、また改めてお伝えしますね。
「延命について考えたいのでアドバイスがほしい」
「家族ときちんと話し合いたいけど、どんなふうに切り出して、何を決めたらいいかしら?」
「ついでに、エンディングノートのあれこれについても教えてほしい」
そんなご相談も、そうみ行政書士事務所では承っております!
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。
公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
我が家では今、レモンが花の時期を迎えています。
レモンの蕾というのは、付き始めが実に鮮やかな赤なんです。
それが育つにつれ段々と薄ピンクになり、最後には肉厚で真っ白な花を咲かせます。ジャスミンそっくりの、良い香りがします。


さて今回は、私の父が他界した時に、ちょっと困った話をしたいと思います。
父が急死してすぐ、引き出しからメモ帳が見つかりました。
どうやら、長く自宅で闘病していた期間中の書き付けのようでした。
日記のようなものや、体調の記録、他愛のない覚え書き…。
日付もあったりなかったり。解読できない文字もたくさんありました。
そんな中見つけたのが、葬儀のこと。
乱雑に「直葬で」と、書かれているページを発見したのです。
直葬とは、通夜や告別式を行わず、安置所から火葬場へ直行することです。
私たちがお世話になった葬儀場の方曰く、「出棺する前に顔を見るという時間もほぼない」ということです。
しかしとにかく、これは父の意思である。と考え、父方の親戚に相談したところ、「お別れ会はしたい」と、猛プッシュされました。
姪の立場である私たちでは、伯父伯母たちに強く出ることもできず、また、今後の長い付き合いも考えて、「揉めたくない」という気持ちもありました。
結果、一番小さなお葬式をあげるということで落ち着きました。
私としては、父の希望通りにしたかったな…と思います。
こんなメモ帳じゃなく、しっかりした遺言書を作っておいてほしかった…。
そんな話を事務所内でしたところ、先生から「そんな時は公正証書遺言が確実!」と、アドバイスをいただきました。
はて、公正証書遺言?
遺言書といって思い浮かぶのは、書斎の引き出しから遺言書が見つかって一波乱!のようなドラマのワンシーン。
ちなみにこの場合は、遺言者本人が書いた遺言書になるので、「自筆証書遺言」というものになります。
では、公正証書遺言はというと、公証役場という所で専門家に作ってもらう遺言書になります。
なぜ先生は公正証書遺言をすすめたのでしょう?
手軽さと費用面で言えば、ダントツで自筆証書遺言です。
ただこちら、勝手に開封できないんです。
そして開封するタイミングですが、初七日から四十九日の法要あたりになることが多いんです。
え…。ということは…?
そう。そうなんです。
葬儀のことを遺言書に書いても、実際の葬儀に間に合わない問題発覚…!
えー!そんなぁ。
では、公正証書遺言はどうか?
こちらの場合、出来上がった遺言書(原本)は公証役場で保管され、遺言者にはその写しである正本と謄本が渡されます。
もし、葬儀のことを遺言にしてある場合、この正本(もしくは謄本)を、喪主になるであろう人に預けておくことができます。
そう。事前に情報共有できるんです。
とはいえ…
公正証書遺言って気軽にできる感じがしない…。
実際、準備は大変だし、時間はかかるし、費用も…ね…それなりにかかります(汗)
ちょっとハードルが高いかな?
でも、遺言書はあった方がいい??
うーん、悩む!
そんな時はまず、エンディングノートを書いて自分の考えをまとめてみるのがおすすめです!
エンディングノート?
と、思った方は、過去記事『エンディングノートと遺言書のちがい』
を是非ご覧ください。
遺言書のこと、エンディングノートのこと、些細なことでもご相談にのります!
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。
公式LINEでも配信しています!登録していただけると嬉しいです。

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは!そうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。 今回はこのテーマを一緒に考えてみましょう。 最近私の身近なところでも高齢者の方の判断能力が落ちてきて、それが原因で家族が悩んでいる というケースを聞くようになってきました。 よく「2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になる」と言われているようにもう決して他人事ではありません。 身近な問題であり、両親そして自分自身も認知症になる可能性があるのだと自分ごととしてとらえることが必要ですよね。 ところで、「うちの親、もしかしたら認知症なのかな?」とその兆候を感じたとします。 そのときになって初めて遺言書を作った方がよいと考え始めるのってどうなんでしょうか。ちょっとあるご家庭の事例を出して考えてみますね。Aさんにはご両親がいましが、昨年お父さまが亡くなられて、 そのショックで元気だったお母さまはぼんやりすることが増えてしまいました。 もしかしたらお母さまはこのままではお父さまを亡くされたショックから認知症などになってしまう のではないかと心配です。 幸いお父さまが亡くなられた時はお母さまがお父さまの財産をしっかり把握してくださっていたので トラブルになりませんでしたが、お母さまにもしものことがあるとAさんご家族は何も知らない状況なので、 相続のトラブルになるのではないかとちょっと心配です。 このような状況の時って、遺言を書いてもらうことって可能なんでしょうか?? みなさんはどう思いますか? 認知症になると難しい条件がたくさん付いてしまいます。 今回は細かいことまで話しませんが、゛認知症になると遺言書を作るのが色々と難しい゛ ということだけ知っておいてください。 じゃあ、「病院で認知症と診断される前に遺言を書いてもらえばいいのかな?」ということをおっしゃる方も いるかもしれませんがそれはもっともめることになります。 なぜかというと、「認知症をごまかして遺言を書かせたんじゃないの??」という疑いが出てくると もめごとの原因になるからです。 だから、ごまかして何とかしよう!!とは思わずに一度専門家の意見を聞いてみるのがいいかなと思います。 認知症といっても、その症状や程度には違いがあります。 普段の生活に支障をきたすほどではなく記憶の能力が低下しているだけの軽度の症状から重度のものまでと 幅広く簡単に判断できるものではありません。 その認知症状によっては、ただちに遺言の作成ができなくなるというわけではないので、 焦らずにプロに相談するのがベストですよ! 弊所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、高齢者がいるご家族の気持ちに寄り添えることができます。 遺言書の作成についてご心配なことがあればお気軽にご相談くださいね。 LINEで簡単に無料相談のご予約もできますし、「どんな相談ができるの?」というような相談事例も ありますのでぜひご活用くださいね。ブログの更新情報もお届け!公式LINEはこちら!

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは!横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。
今年はこの時期花粉が辛く感じる気がします。皆さまは大丈夫でしょうか。

さて前回のブログでは公正証書遺言が出てきましたが、今回は遺言者の直筆によって作成される゙自筆証書遺言゙について
一緒に勉強していきましょう!
自筆証書遺言は遺言者が紙に自ら遺言の内容の全文を手書きして、日付及び氏名を書き署名の下に押印することにより
作成するというものなので、誰でも手軽に作成できてコストもほとんどかからず、多くの方が利用されている遺言書と
言えます。
一見シンプルな内容に思えますが、作成上のルールは細かく定められています。そしてその条件を満たさなければ
遺言書は「無効」となってしまうので実はとても注意が必要です。
では遺言書が無効となるケースとはどんな場合でしょうか?そもそも自筆で作成されていない遺言書は無効になります。
同様に作成日がなかったり、または作成日が特定できないものも無効となります。
例えば「○年○月○日」と書いてあれば問題ないですが、「○年○月吉日」のように書いた場合はどうでしょうか?
この書き方だと無効になってしまいます。
その理由として吉日という表記だと具体的な日にちではないのでいつを指しているのか分からないからです。
ちなみに遺言は自書しなくてもパソコンを利用してもいいのではないか?と勘違いされてしまうことがありますが、
それは財産目録の場合です。
例外的に自筆証書に相続財産全部又は一部の目録(財産目録)を添付するときは、その目録については自書しなくても
よいということになっています。
このように遺言の要件については様々な注意点があるので、自己判断で作成すると無効になったり、トラブルにつながる
ということもあり得ます。
いざ書こうと思っても遺言の内容に迷ってしまったり、どんな風に書いたらいいのかイメージがわかなかったりと一人で
決めるには不安になることもあるのではないでしょうか。

このような皆様のお悩みについてひとつひとつ寄り添えるように一緒に考えていきたい
と思っております。
それぞれのお客さまにとっての最適な遺言についてのアドバイスをすることが可能です。書き方がわからないなどの
遺言のご相談や遺言後のサポートなど、他にも「こんなときはどうしたらいいのかな?」 と不安や疑問に思ったときは
そうみ行政書士事務所までお気軽に ご相談くださいね。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますのでよかったらお友達登録してくださいね!
どんな相談ができるの?という事例ごとの紹介もありますので気になる事があればご活用ください。

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。